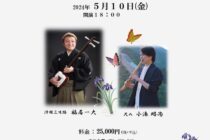The Timeless
Place.


文人墨客が芸術を磨き
日本の行く末を案じる志士が
未来を語った国際サロン
長崎に丸山遊郭が誕生したのは寛永19年(1642)。長崎の市中に散在していた遊郭を一カ所に集めたのが始まりです。外国人を相手とする唯一の遊郭であり、大坂の新町、京都の島原、江戸の吉原につづく花街として賑っておりました。『花月』は丸山随一の太夫屋『引田屋』の楼号で、引田屋本家が花月楼、新引田屋が鶴寿亭、新引田店が養心楼と呼ばれておりました。引田屋は丸山遊郭の開設当初から明治5年の芸娼妓解放令に至るまで続いた唯一の店であり、『史跡料亭 花月』は、引田屋本家の建物と庭園を受け継ぎ、今なお当時の姿を残しております。時を重ねた場所で味わう卓袱料理は、ポルトガルをはじめオランダ、中国など世界と繋がっていた長崎ならではの和華蘭料理です。幕末には多くの要人・文人墨客が訪れ、芸術を磨き、日本の未来が語られた国際サロン。歴史ある場所で、歴史を語る卓袱料理をお楽しみください。

in 1642.


Precious &
Quality
歴史あるお部屋で、
歴史を語るお料理を


お料理
Cuisine
季節を伝える和食と、中国やポルトガル、オランダ伝来の料理をアレンジし発展した卓袱料理。赤い円卓を囲み、和気あいあいと過ごす食スタイルと、長崎独自の和華蘭料理をお楽しみください。


お部屋と庭園
Rooms
日本初の西洋部屋をはじめ、45畳の広さを誇る大広間まで。9つの個性的なお部屋をご用意しております。800坪の日本庭園は、元禄時代からの歴史があり、春の桜、初夏のつつじ、秋の紅葉と、四季の移ろいを教えてくれます。


ご婚礼・宴席
Banquet
披露宴会場は美しい日本庭園を一望する「竜の間」をはじめ、150名収容の大広間「ふじの間」で。丸山芸妓の祝舞、おふたりの初仕事となる餅つき・餅まき、そしてお帰りの際には芸妓衆の送り三味線と、長崎ならではの桃カステラのケーキ入刀など花月ならではの演出で、皆さまにお喜びいただいております。